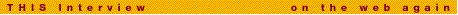
デヴィッド・アムラム。1930年、ニューヨーク州生まれ。フレンチ・ホーン、ピアノ、フルート、パーカッションをはじめ、およそ25カ国以上のエスニック楽器を操る多芸なミュージシャン。そしてオーケストラ、オペラ、映画音楽…さまざまなジャンルで作曲活動を行なってきた「現代アメリカ音楽のルネサンス」。マルチ・カルチュアルな音楽探求の旅を続ける、その足跡を辿るとき、50年代末のビート・ムーヴメントの渦中においてケルアックとの親密な交流があったことは、まさに時代の「必然」だった。ポエトリーと音楽の融合、その可能性について、彼ほど雄弁に語れるものはいない。
 タイトル:デヴィッド・アムラム
タイトル:デヴィッド・アムラム
インタビュー:佐野元春
掲載号:This Vol.1 No.2 '95

――あなたはアメリカで「現代音楽のルネサンス・マン」と呼ばれていますが、まずはそのルーツについて聞かせてください。
デヴィッド・アムラム(以下DM) 子供の頃から、音楽を天職だと思っていました。私の伯父は造船業者で、世界中の港を旅していたのですが、彼の影響でアメリカ以外の数々の民族の存在や、その音楽を早くから知ることができたのです。ちょうど私が五歳の頃、伯父が見せてくれた本の中に、輪になって座るインディアンの写真がありました。そこから、インディアンの音楽に興味を持ったのをきっかけに、どんどんルーツ・ミュージックに対して自覚的であろうと努めるようになりました。言ってみれば、この時期目覚めた感性のままで、私は今も物事を感じる習性があります。
こうした経験は、私に、世界を舞台に生きることを教えてくれました。音楽を通じて各地を旅し、行く先々でその土地の文化や歴史を学び、吸収していく。だから、シンフォニーにしてもジャズにしても、またその他の音楽にしても、今回、日本のアーティストである佐野さんとコラボレートするような音楽も、すべては「世界音楽」だし、そのすべてのルーツが地球そのものにあると思っています。地球上、どこへ旅しても「世界音楽」を演奏している。これが私の信念です。世界はたくさんの美を抱え持っていて、そこから学ぶことは計り知れない、と。
――ジャック・ケルアックと初めて出会ったのはいつ頃のことですか。
DM 1952年のことです。当時私はシンフォニーの作曲をしていましたが、仲間たちとジャズをプレイする機会も多かったから、多分そうした活動を通して知り合ったのだと思います。確か、ケルアックが『路上』を書き上げた翌年のことでした。でも私の周りの人間はみんな、彼のことをクレージーだと言っていました。つまり、純文学界に侵入してきた“よそ者”という風に世間には映ったらしくて…。だって彼はストリート・レベルの話言葉で文章を書いたり、ジャズの評論…今まで誰もやったことのないことを夢中になってやっていたわけですからね。
思い出深いのは、その頃から彼が、全世界の地図を持って仕事をしていたことです。アメリカ、ヨーロッパ、カナダ、メキシコ、そしてアジアのことに想いを馳せていた。特に仏教に傾倒していたため、誰彼と問わず、毎日のようにアジアの宗教や禅の話を吹っかけていたものです。
――あなたが「ビート運動」に触れだした、その当時のことを聞かせてください。
DM まず1957年に初めて、ケルアックと一緒にニューヨークのアート・ギャラリーで、ジャズをフィーチャーしたポエトリー・リーディングを行ないました。これがまことに楽しくて、以来味をしめてしまい(笑)、その機会があるたびに参加していたんです。
'58年になると突然「ビートニクス」という言葉が流行し始めました。ハーブ・ケインというコラムニストが、サンフランシスコ・クロニクル紙に「ロシアにはスプートニクがあるけれど、アメリカにはビートニクがある」っていう記事を書いて話題になったんです。それから急にマスコミがビートを取り上げ始めました。当時私は、ニューヨークのワシントン・スクエアやヴィレッジにたむろしていましたが、ただブラブラしている友人たちがテレビの取材でマイクを向けられ、ビート哲学について意見を求められのをよく見かけたものです。その三週間後には、バーやカフェに座っているだけで、記者にインタビューされるという有様だった。ベレー帽をチョコンとかぶってバーに座っていた連中を「バー・フライ」(バーのハエ)と呼ぶんだけど、彼らはほとんどが「自称」詩人か哲学者だった。でもみんな繊細でいい奴らだった。そして、その一カ月後には、すでにヴィレッジ周辺は黒ベレー帽で埋め尽されていたというわけです(笑)。
――映画『プル・マイ・デイジー』、それに参加したいきさつについて聞かせてください。
DM 1959年に入って、ケルアックやロバート・フランク、そしてアレン・ギンズバーグなどが集まって、自分たちは「ビートニク」なんて輩とは違う――ということで、仲間うちだけで自分たち自身の記録を何か作ろうということになったんです。少なくとも自分たちが見るだけで十分だから、映画でも作ろう、と。
それから話は早かった。全員がアルフレッド・レスリーという、仲間の間で一番広いスペースの家を持っていた画家のロフトに集合しました。撮影用の照明など誰も持ってなかったから、アルフレッドが家のヒューズをいじってムービー・ライトのできそこないを作ったのを憶えています。そういえばフランクも、当時はたった一台のカメラしか持っていなくて、それを木の三脚に立てて使っていました。
私たちは、たった三枚のタイプ紙の台本をケルアックから手渡されただけで、演技の心得も誰一人としてなかった。だいたい、カメラの前に立つということ自体、初めての体験でしたから。それでも二週間かけて、およそ四○時間ぐらい撮影しました。まったくクレージーで、楽しいパーティーっていう感じの現場だった。「愉快で楽しい精神病棟」とでも言うか、おかしくて、みんな笑いころげてばかりだったんです。フランクも笑いころげながらフィルムに収めてるという状態でした。時々カメラが揺れているのは、彼も笑っているからなんです(笑)。
――あなたの音楽も、撮影と同時に作ったんですか。
DM いいえ、撮影を終えてしばらくした後、ケルアックがやって来て、「デヴィッド、これを見ながらピアノとフレンチ・ホルンで音楽をつけてくれないか」って言いました。でも私は即興で音楽をつけるよりも、少し作曲したものをつけ加えたいと彼に言って、時間をもらうことにしました。私がやりたかったのは、いろんな種類のポエトリーをフォーマルな形式に調和させることでした。新しい世界と古いヨーロッパ的な古典の融合というものを試してみたかったんです。
その後、40時間から20分に編集したフィルムを前に、ケルアックがマイクの前に立って「ある朝…早く…この宇宙のどこかで…」という具合にナレーションしていきました。とにかく40時間のものが二○分になってしまったんだから「ナッシング」になってしまったも同然なんだけど、彼がナレーションを即興で入れ始めると「アメージング」なものが出来ていったのには驚きました。
――現在の視点で見直して、その「アメージング」さに変化はありませんか。
DM ええ、映像は本当に素晴らしい。ロバート・フランクの視点はピュアだし、素朴な感じがあの当時の私たちの姿をよく映しています。彼は写真家としての本物の「眼」を持っているんじゃないでしょうか。リチャード・アヴェドンやヘルムート・ニュートンのゴージャスな美しさとは正反対に、日常の普通なものの中に潜む美を、無意識に捕えることができる稀有な感性の持ち主だと感じます。しかし、それ以上にケルアックの即興ナレーションが圧倒的だった。私も音楽の面で、ラッキーにもベストなジャズ・ミュージシャンを集めることができたから、クオリティは非常に高いものが残せたと思ってます。
――その後もケルアックとのコラボレーションは続いたのですか。
DM もちろん。映画の制作以降もポエトリー・リーディングを一緒にやっていたし、まだ結婚前でしたから、私のアパートにも頻繁に遊びに来て、ピアノを挟んで一緒に歌ったりしたものです。当時、彼がたった一人で歌った歌の録音も残っていて、この間そのテープを聞きながら音楽をつけてみたんです。すると四○年前の初々しい気分が甦ってきて、いろいろなことを思い出しました。
ケルアックは作家でありながらも、ジャズ・ミュージシャンようにナチュラルな音楽的素質を持っていたんです。ジャズ的なものに対する感性と理解が、根本にありました。当時のミュージシャンたちがこぞって共演したがっていたのは、そうしたフィーリングが通じていたからでしょうね。彼はよくこう言っていました。「僕はおそらくアメリカのどのライターたちよりも、ジャズがわかっている」ってね。
――ポエトリー・リーディングと音楽のコラボレーションについて、その可能性についてどう思いますか。
DA 音楽家としての立場で言うと、詩によって音楽の「絵」が描きやすくなるし、感性だけでなく思考するチャンスを与えてくれます。でもこのような関係は、何もジャズとポエトリーだけのものではありません。どの土地の文化にも、詩と音楽の結び付きの「原形」は存在しています。
日本の場合――私は歌舞伎を初めて見た時、本当に驚嘆しました。オーケストラがサイドに控え、音楽と言葉、そして演技があれほど一つに融合するというのは素晴らしいことです。土地が変われば表現に違いは生まれますが、私たちが行なってきたポエトリー・セッションと、心を伝えることの衝動において何ら変わりはありません。そして、そのヴィジョンは新しい方法論を取り入れながら、今確実に広がっているんです。
――私たちも今後「マルチ・カルチャー」を標榜して、新しいヴィジョンを探っていきたいと思ってます。
DA 私が思うに、ジャック・ケルアックこそ、あなたが言うところの「マルチ・カルチュアー」そのものでした。アメリカ以外の世界の存在、つまり地球上の他の民族、文化が存在するという基本的なことを、その後の活動によってアメリカを目覚めさせたと言えます。セロニアス・モンク、ディジー・ガレスピー、デューク・エリントン…彼らもみんな「マルチ・カルチャー」だった。謙虚にお互いの文化を学びながら、彼らが創造する作品の中に、特別な意味や魂を込めていったわけです。
プル・マイ・デイジー
ケルアックが『路上』を書き上げた翌年のこと
ニール・キャサディとの大陸横断の旅(1947年)の後、ジャック・ケルアックがテレタイプの巻き紙で『路上』を書き上げたのは1951年のこと。たった3週間で書かれたにも関わらず、原稿が本として出版されたのは6年後、1957年になってからだった。デヴィッド・アムラムと始めてポエトリー・リーディングを行なったというその年、『路上』は50万部を記録していた。
物語のストーリーは、離れて暮らす鉄道技師の夫を訪ねて、妻とその母がやってくるところから始まる。しかし彼の友人たち(ギンズバーグ、ピーター・オロヴスキー。グレゴリー・コルソ、ウィリアム・バロウズら)が入れ替わり立ち替わり押し掛け、詩や哲学談義を始めだしたが、やがては家から追いだされてしまう・・・というシンプルなもの。実現しなかったケルアックの芝居『ビート・ジェネレーション』をベースにしている。その騒ぎの映像の中に、狭い部屋でフレンチ・ホルンを吹き鳴らすアムラムの姿も見られる。

発行所●株式会社佐野元春事務所/東京都港区北青山2-7-28 N.A.ビルディング3F Tel:03-3401-5090 Fax:03-3470-6038 発行元●扶桑社/東京都新宿区市谷台町六番地 Tel:03-3226-8880 編集部●株式会社スイッチ・パブリッシング/東京都港区南青山2-14-18須藤ビルディング2F Tel:03-5474-1431 Fax:03-5474-1430
THIS(年4回発行)禁・無断転載