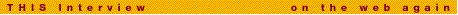
マイケル・マクルーア。1932年カンサス州生まれ。50年中盤、西海岸へ移った彼を待ち受けていた、サンフランシスコのビート・ルネサンス。その片翼を担う存在となった彼は、ボブ・ディラン、ジム・モリソンら、ロック・ミュージシャンと運命的に邂逅し、やがて60年代空前のカルチャー・ムーヴメント“サマー・オブ・ラヴ”の渦中へ身を投じることになる。以来、詩人としてだけではなく、戯曲家としても高い評価を受ける彼は、60歳を越えた今も、若い世代を対象にしたポエトリー・リーディングのクラブ・サーキットを欠かず継続している。現在のパートナー、元ドアーズのレイ・マンザレクとの出会いから、その話は始まった。
 タイトル:マイケル・マクルーア
タイトル:マイケル・マクルーア
インタビュー:佐野元春
掲載号:This Vol.1 No.2 '95

――今回一緒に来日したレイ・マンザレクとは、いつごろ出会ったのですか。
マイケル・マクルーア(以下MM)1965年ごろのことです。私はジム・モリソンの親友で、言ってみればジムの兄貴分といったところでした。『LAタイムス』には、ジムの“師匠”だったと書いてあったけど、まあそんなところでしょう(笑)。それで、ちょうどドア−ズのサ−ド・アルバムのレコ−ディングの時、スタジオに遊びに行ったんだ。そこでジムからメンバ−全員を紹介されて、レイとの付き合いもそこから始まりました。
――その彼とコラボレ−ションをはじめたきっかけを教えてください。
MM 1987年ごろ、私はサンタモニカのナイトクラブでポエトリ−・ソロを行なっていたんです。私の友人で、ジムとも親しかったマイケル・フォ−ドと一緒でした。そこにレイが遊びに来て、マイケルのパフォ−マンスに合わせてピアノを弾きだしたんだ。その時私はレイの演奏を聴き、レイも僕の朗読に真剣に耳を傾けてくれた。そしてレイは僕に「一緒にやらないか」と言ってくれたんです。私もレイの演奏を聴いて、彼はピアノを弾かせても、ハモンドオルガンを弾かせても素晴らしいミュ−ジシャンだということがすぐわかった。でも、それ以上にレイは詩を愛していたし、私の詩を理解してくれたんです。その六週間後には、一緒にパフォ−マンスをすることが正式に決まりました。
――貴方はこれまで、ボブ・ディランとの共演を通して、言葉と音楽のコラボレ−ションの可能性を僕たちに示してくれました。
MM 1965年ごろだったと思うけど、ディランが僕にオ−ト・ハ−プ(Autoharp)をくれて、歌うように勧めたので、少しの間、歌をやってみたことがあります。六七年に行なわれた「The First Human Being」でも歌いました。その後はミュ−ジカルの歌詞をずいぶん書いたし、ジャニス・ジョプリンが歌った「メルセデス・ベンツ」という曲の詞を書いたりしたものです。だから、私の中では言葉と音楽の二つは、無意識に融合されていたと言うべきでしょう。
――60年代、ロックンロ−ルとビ−ト・ポエトリ−とがコラボレ−ションしていた当時のこと、特にサンフランシスコで何が起こっていたかについて少し聞かせてください。
MM それは…1955年に遡ります。その年、シックス・ギャラリーで行なわれたイベントで、私は生まれて初めてポエトリー・リーディングを経験しました、アレン・ギンズバ−グが初めて『吠える』を朗読したときです。私はゲイリ−・スナイダ−に会い、また、そこにはジャック・ケルアックもいました。偉大なるアナ−キストであり、哲学者であり、詩人であるケネス・レクスロスが主催したこの会をきっかけに、我々はポエトリーを通して、自然、環境問題、反戦、政治、反マッカ−シズム等について、自分たちの意見を述べるようになったんです。人々、特にサンフランシスコの若者たちはこうした情報に飢えていて、それらを本当に心の底から求めていたから、我々の言葉を深く受け止めてくれました。
その直後から、私たちは「叛逆者」や「革命児」とか呼ばれるようになったのですが、60年代に入るとそこにロックの概念が加わってきました。たとえばビ−トルズは、自分たちのバンド名を“The Beats”からとったと言われていますが、彼らはビートの詩に親しんでいて、彼ら自身の歌詞も、だんだん深みが増していきましたね。ロックンロ−ルの起源は、ハウリン・ウルフやウィリ−・ディクソンのようなブル−ズやブラック・ミュ−ジックにありますが、それらもビートの中に生きているんです。
――貴方たちの活動は、ロックだけではなく、60年代のカウンター・カルチャーの礎となりましたね。
MM 60年代、ロックの歌詞というのはとても知的で、みんなそこからいろんなものを学んでいたのです。ただリズムに合わせて踊っているだけではなく、そうした言葉に反応した“季節”でもありました。当時、ロック・グループと詩人たちは、ひとつの大きなコミュニティ−を形成していたんです。私もちょうどその頃、ジム・モリソンを始めとするドア−ズのメンバ−や、ボブ・ディランと一緒に過ごしていましたから、そうした状況を目の辺たりにしながら“季節”を過ごしていました。
しかしその後、アメリカのロックンロ−ルはオ−バ−グラウンドな世界に引っ張り出されてから商業化され、ビ−ルとテレビと、そしてテニス・シュ−ズと引き換えに、ア−ト・コミュニティ−やラディカルなコミュミニティ−から買い取られていってしまった。ロックは分裂を起こし、歌詞もどんどん散漫で陳腐なものになっていってしまったんだ。
――現代において、ロックはもう一度、以前のような本来のパワーを取り戻せると思いますか。
MM 努力はしているつもりです。レイと出会った時に、我々がやろうと決めたことの一つは、ビートやブル−ス系の黒人たちが元来持っていた知性を取り戻して、オ−ディエンスに提供しようということだった。既製のものには手をつけずに、新しい共生関係を生み出そうと話し合ったんだ。
レイはバリ島の音楽みたいなものからベ−ト−ベンみたいなものもやれば、ブル−スも、レイ・マンザレク流のロックンロ−ルも、ジャズみたいなものもやる。 もちろんどれもすべて彼ががやっているわけだが、それらがみんなレイの音楽の中に一体化している。これに、ビ−トとしての意識の流れが私の言葉の中で合わさり、それらを一つの有機体として昇華させる。我々は1955年に存在したものを、新しい方法でもう一度人々に提供したい……それを私は「ニュ−・サイケデリック」と呼んでいます。
――ソニック・ユ−スと共演したいと言ってましたが、90年代の今もカウンタ−・カルチャ−に興味がありますか。
MM もちろん。ギンズバ−グやジム・キャロル、ドア−ズの歌詞を書いていたロバ−ト・ハンタ−と共演しながら、レイも私も、今もってカウンタ−・カルチャ−にはとても深く関わっていると思うよ。たとえば、我々は今も、大学のキャンパスを訪れたり、ジャック・ケルアック・フェスティヴァルに参加したり、アメリカ中のミュ−ジック・クラブを回ったりしながら、若い世代を前にプレイしている。そして彼らの想像力や意識が成長するのを助け、独自の政治意識や環境問題への関心に目覚める突破口を作ってあげるということにとても積極的に関わっている。
ビートとは常に、環境運動の文学的一派だった。だから今回、東京でのパフォ−マンスを見ても、我々のやっていることの大部分は政治的で、環境問題に深く関わっているということがわかってもらえると思う。こういうやり方というのは、ある意味では今日のロックでは求心力を失っているというか、ほとんど存在しないに等しいけれど、我々はとても直接的に言葉を発していると思う。
――環境問題や政治に対する、アメリカの若いオ−ディエンスの反応はどうですか。
MM 彼らはとてもオ−プンで、こうした問題について聞くことを喜んでいる。そして、総立ちになって我々に拍手を送ってくれることも多いんだ(笑)。
――それは、若いオ−ディエンスが貴方を尊敬しているからだと思いますが。
MM でも、我々のオ−ディエンスはとても変わっているよ(笑)。大変年齢層が広くて、モヒカン刈りの頭をした少年から、もっと年長のジャズに精通した人、ドア−ズのファン、詩のファンに至るまで、あらゆる年齢、あらゆるタイプの人がいる。だいたい25歳以下の若者中心だが、私ぐらいの年齢の人や、もっと年長の人も来る。とてもヴァラエティ−に富んだオ−ディエンスだね。
時々はドア−ズのファンばかりのこともある……ニュ−ヨ−クの“ボトムライン”でのことだ。若い男のオ−ディエンスはみんな黒いレザ−・パンツに、ジム・モリソンTシャツを着ていた。彼らが「『ハ−トに火をつけて』をやれ!」と叫ぶので、「もし『ハ−トに火をつけて』を歌ったら、みんな五分後にはドアを開けて出ていってしまうに違いないよ」と言い返してから朗読を始めた。でも、最後はみんな立ち上がって“That's Visionary Man!”と叫んでくれたよ(笑)。
――MTVに代表されるような、現代の若者たちによるスポ−クン・ワ−ズのム−ブメントをどう思いますか。
MM 「ロラパル−ザ・フェスティヴァル」って知ってるかい? 去年の「ロラパル−ザ」にレイと行ったけど、とても楽しかったよ。そこに出演したスポ−クン・ワ−ズの連中の中には、とてもいい若者もいた。たぶん我々も、次のロラパル−ザに参加すると思う。若いオ−ディエンスも好きだし、スポ−クン・ワ−ズをやってる若い連中と一緒にプレイするのも好きなんだ。
――90年代の若者たちによるスポ−クンワ−ズと、50年代の若者による運動との間に、文化上の違いはありますか。
MM まず、90年代のオ−ディエンスと五○年代のオ−ディエンスについて話しましょう。その二つのオ−ディエンスはとても良く似ている。どちらも中央の権威主義的な文化から隔絶されていて、絶望していて、そこから遠ざかろうとしている。そして、彼らの才能や知性や、音楽と詩から得たイマジネ−ションや経験を、形にするきっかけを求めている。50年代の若者は飢えていた――それは90年代も同じことさ。
60年代に入るとオ−ディエンスは、もっとロックに深く関わっていきました。当時は、ロックがラディカルな人々のコミュニティ−から買い取られてしまう前で、まだ若者の代弁者だったってわけです。
――最後の質問です。貴方の著作『Scratching the Beat Surface』はどのような経緯で書かれたのですか。
MM『Scratching the Beat Surface』は、私の旧友で偉大な詩人のチャ−ルズ・オルソンの作品をもとに、詩に関する講演シリ−ズを行うようニュ−ヨ−クの大学から依頼されたのが土台になっています。オルソンについて話をするうちに興に乗ってきて、ビートについて触れ始めた。自分自身のこと、さっき話した初めてのポエトリ−・リ−ディングのことなどについて。それから政治や環境問題についての信念のことも。それがこの本の前半部分になっています。後半は僕が書いた長文のエッセイで、詩人の目からみた生物学―― “Meat as consciousness”(=意識としての肉)という観念的なテ−マの評論としてまとめられています。
ケネス・レクスロス
ロラパルーザ
Scratching the Beat Surface
The First Human Being
1967年1月14日土曜日の午後、サンフランシスコのゴールデンゲート・パーク内にあるポロ・グランドで行なわれた、大規模なフリー・コンサート。グレイトフル・デッド、ジャファーソン.エアプレイらシスコ・ロック勢とギンズバーグ、スナイダー、ファリンゲッティらビート詩人たちが参加した。その後、世界中に「ビートイン」は飛び火した。
1905年生まれ。詩人以外にも画家、戯曲家などの肩書を持つ、ビートニクスの指導者的存在。彼の企画によるシックス・ギャラリーでの朗読会から、シスコのビート・ルネサンスは始まった。
毎年夏の間、一ケ月という期間を費やして全米ツアーを敢行するオルタナ系ロック・フェス。もともとは91年、ジェーンズ・アディクションの解散ツアーとして企画された。昨年はスマパン、ビースティ、L7らと共に日本のボアダムスも参加。そのサブ・ステージでは、スポークン・ワーズのパフォーマンスもなされている。
「ビートの表層をかきむしれば」というタイトル通り、ビートにまつわるエッセイや評論でまとめられている。ケルアックの『路上』出版から25周年を記念して、ビート作家が集まった「ケルアック会議」のあった1982年に出版された。最近では93年『Lighting the Corners』というエッセイ&インタビュー集を発表している。

発行所●株式会社佐野元春事務所/東京都港区北青山2-7-28 N.A.ビルディング3F Tel:03-3401-5090 Fax:03-3470-6038 発行元●扶桑社/東京都新宿区市谷台町六番地 Tel:03-3226-8880 編集部●株式会社スイッチ・パブリッシング/東京都港区南青山2-14-18須藤ビルディング2F Tel:03-5474-1431 Fax:03-5474-1430
THIS(年4回発行)禁・無断転載