「21世紀のポップ・チルドレン」
佐野元春インタビュー
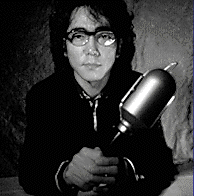 現在、ソニー・ミュージックエンタテインメントのサーバにアクセスすると、ファンの有志によって作られた佐野元春のホームページを見ることができる。
現在、ソニー・ミュージックエンタテインメントのサーバにアクセスすると、ファンの有志によって作られた佐野元春のホームページを見ることができる。メジャー・レーベルに在籍するミュージシャンのなかで、佐野元春はこの有志たちの試みをいち早く支援し、著作権問題も含めて来るべきメディアへの対応に果敢に乗り出している。
アルバムをリリースすれば、常にヒットチャートのトップ圏内に入るビッグ・アーティストという顔をもつ半面、80年代より雑誌の発行やカセットブックのリリースなど、いくつものメディアを駆使して自己表現を試みてきたアバンギャルディスト(前衛家)でもある。
ビートニクに思いをはせ、経験主義を重んじる佐野元春にとって、デジタル・テクノロジーは新たなる友となるか、またアーティストが迎える21世紀は明るいのか?新作のレコーディングにとりかかった彼に「ワイアード」が聞く。
intervew ワイアード
photo ジュン・タカギ
html制作 深沢英次
個人的な体験、
ケルアックとインターネット
WIRED(以下、W):デジタル・ツールとの出会いについて、 個人的な体験を教えてください。また、
そこから何か触発されて作品に結実したということはありますか。
佐野(以下、S):80年代の中頃にニューヨークで生活していましたが、ちょうどその頃、街ではダウンタウンよりヒップホップがわき起こっていて、それが音楽からアートの分野にまで広がりながら確立していったという背景がありました。
その中でミュージシャンにとっていちばん興味があったものといえば、 DMXというマシンです。DMXマシンというのは自動ドラムですね。黒人やプエルトリカンたちが、ラップのフォームを作っていたんです。それまで僕は機械がビートを聞かせてくれるなんて想像もしなかった。それで、僕も楽器屋へ行ってDMXマシンを買い、当初誰もやっていなかった日本語のラップ音楽を作ってみたという経緯があるんです。だから当時の僕の部屋には、ミキサーとDMXマシンと僕自身と、その3つしかなかった(笑)。
毎日、日本語によるラップを作っては、 黒人やプエルトリカンの仲間に聴いて喜んでもらっていた。一緒に遊びたかったんですね。それが目的でDMXマシンを購入したんです。僕にとってユニークでしかもエキサイティングないちばん最初のデジタル・ツールはDMXマシンでした。
それからしばらくして、Macintoshの最初のモデルが発表されたんですが、その時Macintoshを使って音楽を制作する友人がいたんです。その頃にパーソナルなレベルでのコンピュータといわれるものが、初めて音楽制作のプロセスとして、いよいよストリート・レベルで導入され始めるんだなと感じました。
これからこの手法は大きく広まっていくだろうなという予感がしました。85年頃かな、その時点で僕は音楽的戦略をコンピュータを使って練り上げようという気持ちはなかった。それがデジタル・マシーンとの意識的な出会いです。無意識の出会いはもっともっとたくさんあったんでしょうけどね。
W:最初からデジタル・ツールに対する拒否反応はなかったのですか。
S:ありました。僕は小さい時から経験を重んじていて、自分が痛い目に遭い、血を流して初めて物事を知り、自分が感動して心が動いて、初めて物事を知るという、自分の中に強烈な独特の物差しをもっているんです。
その経験主義的なものの考え方が、当初コンピュータに触れた時の最初の拒否反応を示したのかなと自分では思っています。
W:実際、創造活動の中においてデジタル・ツールはどんな役割を果たしていますか。
S:音楽制作でいえば、バンドのミュージシャンたちに僕の考えをできるだけ分かりやすい形で披露するために、僕の側で6、7割ファイナルの形に構成したトラックをコンピュータ上で作成し、それを最終的にミュージシャンに聴いてもらう。そして、ときにはその作成したデータを流用することもあるし、ときにはそのデータがただの参考になってしまうケースもある。
曲によって、あるいは曲にのる言葉によって、あるいは僕がスタジオの中でギターで歌うこともあったりと、ケース・バイ・ケースです。
W:自分の提示したものがいろいろな形で発展していくわけですね。
S:そうです。音楽制作では常に複数の人間たちがかかわっているので、ある程度僕の方でほかのメンバーのスポンテニアス(自然発生的・無意識的)な何かを期待する制作物の場合には、今のようなやり方で作品を作る。
けれど、たとえば1986年に出した『ELECTRIC GARDEN』【*1】の音楽のような非常にプライベートな音楽、つまり一人で何もかもやりくりしてしまうのだと最初から割り切っているプロダクツの制作については、コンピュータだけで仕上げてしまうケースも多いですね。
W:『ELECTRIC GARDEN』は、当時としてはメディアミックスというか、今でいうマルチメディアでしたよね。
S:全くその通りです。ひらたく言えばグラフィックと音とテキストですね。この3つを有機的に働かせるアートといえるのではないでしょうか。
あの時代にできるものとして採用したのが、 あのカセットボックスだったんです。
W:あらゆるメディアに挑戦していくそのモチベーションという点で非常に興味があるんですが、それはやはりアーティストとしてのクリエイティビティの枠を拡大していくためのものなのでしょうか。
S:モチベーションはもっと原初的なものです。人から愛されたい、人から憎まれたい、そうした原初的な感情ですね。あるいは意思の交換を自分以外の他者と取り交わしたいという欲望に近いものがモチベーションになっています。人を喜ばせたい、悲しませたい、献身したい、騙したい。いろいろなモチベーションが僕の中でたぶん混在しているだろうと思います。
そうしたモチベーションがおそらく作品としてさまざまな形でかかわってくる。自分が生み出したものを、適切な居場所に僕の方で割り振っていくという、ここがいちばん大変で、また僕が意識的になるところなんですね。
この作品はこのメディアに割り振った方が人々と最高に何かを分かち合えるかもしれない、この作品はこのメディアに居場所を割り振ってあげた方が作品にとって居心地がいいかもしれない、といったことを考える。そこはものを作る側の責任の範囲だと思います。
19世紀の人たちは考える必要はなかったでしょうけどね(笑)。
W:コンピュータをコミュニケーション・ツールとして使うとき、たとえばインターネットというメディアを介して、ネットワーカーとしての体験から生まれたもの、あるいは生み出そうとしているものはありますか。
S:まず、インターネットの利用は、その対し方によって違ってくると思うんですね。
インターネットをどう捉えるか、あるいはインターネットに対してのかかわり方で変わってくる。僕の場合は情報収集の支援ツールとして役立てている。
以前、雑誌「THIS」【*2】を編集する中で、かねてから非常に興味のあったジャック・ケルアック【*3】という作家を取り上げようとしたことがあったんです。そこで、そのケルアックという作家が生まれた背景をできるだけ正確に読者に伝えるために実際にジャック・ケルアックの生まれた町に行こうとした。ジャック・ケルアックが、その町でどんな幼少時代を過ごしたかといった環境、そして彼を取り巻いてきた人々、その周辺の調査をして、彼の作家としての姿を正しい形で表現しようと思ったんです。
でも、それにあたっての資料が日本のどこにもないわけですよね。ケルアックの幼少時代が書かれた本で翻訳された本はどこにもない。それで僕はインターネットを使って検索を始めたんです。最初は、「Jack
Kerouac」「Beat」と、思いつく限りのキーワードを使って。
で、そのうちに「The Beat Generation」というひとつのサイトにぶち当たった。これは、やはり“ビート”に興味をもっているあるアメリカ人が個人で出しているサイトなんですね。それで、その個人がビートの流れから、作家のプロフィール、それから作品に対する自分の考え、人々の考え、ひいてはエリアにいる作家たちの最近のアクションに至るまでを克明に紹介している。
それで、「ケルアックに関する取材をもくろんでいるんだけれども、何か方法はないものだろうか」と率直に申し込んだんです。すると即座に電子メールが返ってきました。自分も記事の制作に協力したいと。
そして、ジャック・ケルアックの生まれた町の状況っていうのかな、彼の生まれた場所の地図などの、ケルアックについて非常に細分化され、専門化された情報が彼から得られたんです。
僕はそれをダウンロードしたものを持ってその地に飛び、まるでもう10年前からその土地を知っているかのように車で町を徘徊し、ジャック・ケルアックの生家に立ち、あらかじめ入手した資料を基にその周辺を取材した。普通だったら1週間から1カ月くらいかかる取材が、たった1日でできてしまった(笑)。
W:場所はどこですか。
S:マサチューセッツ州のローウェル。スモールタウンですね。きっと日本で国会図書館に行っても、なかなか検索はできませんよね。たまにぶち当たったとしても、ローウェル市の人口ぐらいしか分からないでしょ。産業基盤の統計のような概略的な情報しか得られない。そこにジャック・ケルアックが生まれて育ったなんてことは、たぶん書かれていない。
だから、インターネットをひとつの情報収集の支援ツールとして捉えた場合には、そのサブジェクトが細分化され、その先で専門化された情報を手に入れることができるという点で、非常に有効だという気がします。
ホームページと著作権、辺境のメディア冒険者
W:コピーメディアが楽譜だけだった時代に比べ、現在は0と1の信号になりました。すでに技術的には可能といわれる同軸ケーブルや光ファイバーを通しての商品流通を考えると、著作権の無法地帯を通過しなければならないと思いますが、そのような時代で著作権についてはどう考えていますか。
S:その前に、インターネット上で「元春ページ」の立ち上がった経緯を説明したいのですが、ある人から僕の元に電子メールが届いたんですね。
ある一人のファンがインターネットを使って、僕に関することで、こんなことがやりたい、あんなことがやりたいとメッセージを送ってきたんですね。僕もその時点で興味があったので、
承諾しました。
彼はコンテンツをもっていましたから実際に彼がやりたいことをホームページ化する、インターネット上に載せるという作業自体は、非常に簡単なんです。
だけど、いちばんネックになっているのはやはり著作権。この著作権の問題を誰かがクリアしていかなければいけないけれども、僕のビジネス周辺の人はまだインターネットについてあまり深い知識はなかった。僕が契約しているソニーもその時点ではまだはっきりわかっていなかった。
だから、僕が中心となって著作権の問題をクリアして、僕自身が、彼らが比較的自由なスタンスでホームページを運営できるようなお膳立てをしなければ対応できなかったのではないでしょうか。
そして僕の音楽、すべての楽曲を管理しているソニー、それから僕と彼らをはじめみんなが協議をして、その協議の中でひとつずつ(問題点を)つぶしていったんです。画像についてはどうなのか、音についてはどうなのか、その使用期限についてはどう対処すればよいのだとか。そういった実際的なディスカッションを行ったんです。
ただ、どうしても現行の法律(著作権法)ではケアできない、こぼれるものがたくさん出てくることに気づく。だとすれば、各論は各論として対処することにして、総論として全体を助けるような形でいこうじゃないかといったような討議が続いた。
だから、テストケースとして半年間やってみようということになったんです。その半年間で何か問題が出てきたら、その問題をクリアしていくというように、とにかくトライ&エラーの精神でやってみたんです。何が起こるかわからないわけだから、まずインターネット上にそのホームページを作ることでコミュニケーションが生じたときに、さまざまな、良いケーススタディも悪いケーススタディも、その先のケーススタディをとにかく集めようという積極的な意見が出てきた。そして、現在のあのような形ができたわけです。
だから、周囲の理解がなければ、ああいったアーティストのホームページを運営していくのは、なかなか難しいのではないかと思います。
今よくいわれるマルチメディアという概念に対して、まずそれを見守る人がいる。それから、それを推進する人がいる。マルチメディアという概念に対してさまざまなスタンスに立つ人がいる。僕やホームページを作ってくれている彼などはマルチメディアの推進者という立場に立っている。その推進者がとりあえずの前例を作っていき、その中でエラーが見つかったなら、それに対して著作権の保有者が中心になって対処していく。それによって、どう解決策を生み出していくのかという事例を蓄積していくという時期なんだと僕は認識しています。
だから、やる前からいろいろな著作権のトラブルでアーティストを失ったり、発表の機会を失わせたりするのは、僕は得策ではないという考えです。
今は“マルチメディア冒険者”といったらいいのかな(笑)、“マルチメディア推進者”といったらいいのかな、まあそういう立場に属する人たちのケーススタディをどんどん作る時期だと思っています。それが僕の基本的なスタンスです。
W:起ち上げてからどのくらいの期間がたっていますか。
S:4カ月くらいです。
W:今の時点で良いケース、悪いケースが具体的に表面化してきたものはありますか。
S:実際に問題が起こったときには僕が解決するという形になると思いますが、今の時点で特に目に余るっていうか(笑)、このまま放っておいたらとんでもないことになるといったような事例はまだありません。
ただ、アーティストのホームページという存在自体に興味をもっているマルチメディア・ビジネスマンたちが非常な勢いでアプローチしてきてますね。こんなのを作ってもらえないかとか、これをCD-ROMの形で出したいとかということですね。
新しい文脈,ブラックビニールとCD
W:インタラクティブなメディアにおいて、テクノロジー自体が今後の作品発表のモチベーションとなるものでしょうか。もしそうだとしたら、 90年代の『ELECTRIC GARDEN』はどうなっていくと思いますか。また具体的なアイデアとして実行したいことはありますか。
S:まず、そこにどんなコンテンツがあるかというよりも、インターネット上においての新しい文脈(コンテクスト)作りですよね。ここがいちばんの課題なわけです。
ただコンテンツをぶら下げるだけであれば、それは今すぐにでもできます。しかし、そこに新しい意味をもった文脈がない限りは面白くないという課題が僕の中にありますね。それを、今は日々考えてますね。
新しい文脈とはどういうものなのか、そしてそれを説明するとしたら何が必要なのか、どんな知識が必要となってくるのかを考えてます。そこを自分自身で解釈しながら立ち上げていこうと思っています。
W:コンテクストは簡単に生まれてくるものではないですよね。
S:ええ。ひとつは、技術の問題とも並行して考えなければいけないことなんですね。
現状のHTMLができることの中で、 自分のやりたいことが制限されてしまうような場合も一方ではある。特に僕はテキストにも興味があるし、グラフィックにも興味がある。それ以上にサウンドにも興味がありますから、その再生の仕方、たとえばあるマシンで再生する時に、最初にもくろんだことが失敗した場合はどうするのか。そういう問題を考えなければいけない。
ただ自分のやりたいことと、技術的な進歩を並行させて、『ELECTRIC GARDEN』の90年代版の実現に向けて睨んでいこうと考えています。今、現状の僕に考えられて表現できるもの……それはまだ、黎明期といっていいかもしれないですよね。
ただ、そうした技術の黎明期の中にあっても、きちっとしたコンテクストを提供することは、僕は不可能ではないと思っています。
W:一方では技術の満たないことを逆手にとった表現というのもいくつかありますよね。
S:それもまた楽しいですね。
W:現在メジャーレーベルではできないものを、インディペンデントのアーティストたちが自由な形でレコード会社と契約せずに直接ネット上で自作に課金して公開し、マーケティングも自分でやろうという動きが一部にあります。そのような形で、たとえば楽曲だけをダウンロードさせるとかリスナーと一緒に曲を発展させるといった、ネットによるリスナーとのダイレクトな交流を発展させていくということも考えられると思いますが。
S:考えられますね。ただ、そこで僕の考えというのは、自分が作った音楽、あるいは創作物の性質に合わせて、その適切な居場所をその作家が割り振っていくものだという、ここの意識が今の時点でなければいけないなと思ってます。
僕には自分の作ったソフトを何もかもネットに流すという考えはない。それぞれが、それぞれの適切な場所をもっている気がするのです。
それから、今あるパッケージ商品がすべてノンパッケージになっていくとも僕は思わない。僕はアナログ・レコードで育ってきた世代ですから……昔はブラックビニールというものに対して、ソフトを包む紙でできた30センチ×30センチのアルバムジャケットにある種のアートが施されていて、僕らはレコード屋に行くとその紙の感触を確かめたり、そのパッケージのビニールを破いてそこから香り立つ特有のレコードの匂いを楽しんだりといったような経験をしている。時代を経て昔のブラックビニールはピカピカ光るディスクになり、それを包むパッケージはボール紙からプラスティックケースになったわけですね。
それはそれで、レコードショップに行ってまた違った感触を楽しむことができるし、パッケージを開いた時にアートワークが施されているという形で、触れる人にさまざまな体験が蓄積されていく。そんなひとつひとつの貴重な体験を、ある瞬間からすべて台無しにしてしまって「君の考えは違うんだよ、新しい時代には新しい時代のパッケージというものがあって、新しい時代の音楽というものは、こういうものになるんだよ」と、強制的に誰かから指示されるのは僕は嫌なんですね。だから、そういった意味では住み分けは生じてくると思う。
ある種の音楽に対しては、アートワークが重要なものとしてその時のパッケージに採用されて流通されるだろうし、ある種の音楽はパッケージの必要ないものとして供給されると思う。それは有償なのか無償なのかということも含めて、それぞれがそれなりの形となった音楽として出てくる。
これは音楽だけでなく、グラフィックや写真だとか、絵画、あるいはポエトリー、小説など、人間の創造するアートというのはすべて同じ道をたどっていくものではないかと思います。
僕はアーティストですから、自分の作ったものでお米買ってるわけですから悠長なことは言ってられないんですが(笑)、自分のアーティストとしての経済活動を別にしても、非常に面白くなってきていると思う。
新しいポエジー、妄想としてのマルチメディア
W:活字媒体にしても、より住み分けがはっきりしていくと考えますか。たとえばサンフランシスコでは詩人たちがサーバを起ち上げるという話も聞いています。そこでテクノロジーが発展していく過程で“ポエジー”は発生するのかという課題が提示されると思うのですが。
電子ブックにしても、本を読んで得たものと同じような感動や、自分の人生を変えられるほどの体験は得られると思いますか。
S:たとえば、それまで使われてきたオーラルな表現や、活字を使って表現してきた雑誌の内容自体を、そのままデジタル・データにしてオンライン化しても、何も起こらないと僕は思っています。
もちろんそれぞれ無名な詩人たちの、発表の場にはなり得るかもしれない。でも重要なのは、ネットワーク上で新しい“ポエジー”とは何かということの追求、すなわち紙媒体からは得られなかった何か、あるいはオーラルの表現では得られなかった新しい表現とは何か?すなわち、これもコンテンツではなくて新しいコンテクストの追求ということですよね。それが課題として突きつけられている状況なんだと思います。
つまりデスクトップ上に現れる“ポエジー”ということでいえば、いわゆる紙に印字された「詩」そのものではないのか?もっと別のものではないのか?という問題提起をしていく中で、(デジタル・ツールは)ハイパーテキストという概念の有効な手段として……つまり新しい“ポエジー”を生み出す有効な手段として活躍するのではないでしょうか。
もっともっとたくさんネットワーク上に新しい“ポエジー”が生まれるチャンスは無限にあるし、実際に興味のあるアーティストは、もうすでに探し始めているという状況だと思います。
W:たとえばCD-ROMを出すアーティストはすでに現れていて、インターネットとはまた違ってある程度の決まった容量の中で創造されるものですが、マルチメディアの中でCD-ROMをどのように捉えていますか。またそういったインタラクティブな作品を制作する予定はありますか。
S:レコーディングスタジオの中で使うマルチメディア、家で使うカセットテープやDAT、あるいはネットワーク、CD-ROM、そうしたメディアのすべては、顔の違った、また性格の違ったキャンバスにすぎないわけですよね。つまり僕はそれぞれのキャンバスがもっている性格に合わせて適切なスタンスをとる。ここを強く意識するんですよね。
たぶん僕だけではなく、ものを作ることに熱心な人たちはある程度そうではないかな。
アーティストたちがそれぞれのメディアに対して計算高くつき合っているとは僕には思えない。「これだったら自分の中のあれを表現できるな」「ああこのカセットだったらあれを表現できるな」といった直観的なエクスタシーを感じてつき合いが始まっているのだと思います。
その意味では確かにCD-ROMは興味深いと思います。ただ、多くの人が言うような“何ができるか”ではなく、“何をしたいのか”という、
そこが問題になってくると思うんです。
W:具体的に“何をしたいのか”ということで手がけた作品というのはありましたか。
S:幕張メッセで毎年Mac World Expoが開催されますよね。初期の頃でしたが、その時、マルチメディアに興味がある人でマシンを使って何かを作ろうという話がありました。当時、僕も表現者として興味があったので引き受けて発表した作品がありました。
そのMac World Expoで発表した作品は、当時のいちばん最速のマシンだったMacintosh
II cxを使ったものでした。非常に大きな画像データからなる僕の写真と音をレーザーディスクからつないでくることにして、コンピュータ上ではインタラクティブな情報を提供するという、今でいうマルチメディアの実験的な作品ですね。
九州のプログラマーやデザイナーたちと一緒に1週間かけて作り上げたアートで、「Dovanna」という作品をMac
World Expo会場で披露したんです。僕にとっての最初のマルチメディア作品となったんですね。
それは85年に僕が発表した『ELECTRIC GARDEN』の中の「Dovanna」と呼ばれる作品をマルチメディアで表現したらどうなるのか、ということを数年後に実現したわけです。
まだMacintosh II cxが最速の時代でしたから、89年頃だったと思います。その当時はまだMacintoshだけでなく、どのコンピュータも映像が取り込めなかった。しかもキャプチャーするボードなんかもないし、圧縮の技術だってまだ開発途上でしたし……。
その「Dovanna」という作品は僕の実写の顔がまずあって、その後ろにちょうど嵐のときの雲が流れて、そこで僕の顔が常に微妙に変化する。そして、それぞれにクリックするポイントを設定してあって、目をクリックすると画面の僕が見ている別の風景が映し出されて、口をクリックするとオーラルの表現に変わるといったようなものが2分か3分間ぐらい続くというものです。
また、あるポイントをクリックすると僕の詩句表現に連動して(僕がDovannaという女性について読み上げていく)Dovannaの身体のやわらかなラインに沿って僕が触るというような動画となる。その瞬間に、僕の頭脳をクリックすると、巨大なエクスプロージョンがドカン!とくるといったものでした。
これは僕の非常に個的なオブセッションといったらいいのか、妄想といったらいいのか、それを強引にマルチメディア化した作品となっているんです。その時のシステムはレーザーディスクとMacintosh
II cxだけだったけれど、僕はその時点で自分が“何をやりたい”のかというのを明確にもっていた。ただ、なかなか自分のやりたいことを100%は表現できなかったですけれど……。今だったら70から80%くらい、
将来は100%表現できるかもしれないですね。
W:その制作過程はどのような形態でしたか。
S:クリエイターが3人、プログラマーが1人。アーティストが画像を制作して、それがすべてプログラマーのところに渡り、僕の指示で総合的に作っていくというオートメーション・システムでした。だから今でいうマルチメディアの制作システムの原初的なものが、すでにあったと自負してるんです。
21世紀のポップ・チルドレン、
そして僕らは寛容になる
W:新しいメディアが岐路に立っている中で、創作活動において、特にインターネットを使って何かに触発されるということはありますか。
S:インターネットに限れば芸術的な何かを触発されるというのはめったにないですね。今のところ情報収集の支援ツールにとどまっている。
ただ、地球上の蜘蛛の巣のようなネットワーク、これは概念ということならば、インターネットをテーマにした曲というのは書けるし、書きたいと思う。そういう点でソングライターとしての刺激はある。「インターネット・ラブ」なんていうタイトルはどうかななんて(笑)、そんなことは考えています。
W:『Pop Children with the New Machine』【*4】という作品で現代の子供たちにメッセージを送っていますが、21世紀のPop Childrenとはどのような定義になっていくと思いますか。
S:まず僕自身として振り返ってみると、積極的でいて、同時に無意識的なかかわりをして元気のある子供たちを支援する視点と、当時のそうした状況に対する多少シニカルな視点も盛り込んだ気がします。
明と暗を3分間の中にどうにか盛り込むように頑張っていくというのが、僕流のソング・ライティングだといえます。曲の中で重要なラインというのは「君は3個のダイヤモンドを掘りあてて、そして4個のダイヤモンドをなくしてしまう」という、このラインがあの曲の中では際立っていたんじゃないかなと思っています。
僕の目に映る都市に生きるPop Childrenの現状は……具体的にいうとデスクトップに向かい、
毎日椅子に座っている彼らの現状というのはたぶんあの詩の中に集約されていると思っています。
今日まで人間の“意識”はいろいろな形で創造されてきたけれど、今後、人間の“無意識”は形になっていくのだろうかと考えます。そういう意味ではインターネットというデジタル上に、個的で無意識なオブセッションがぶら下がっていくのではないかと思います。で
は、それから僕らは何を得るか?多様性、辛抱強さ、許容性を学んでいくのではないでしょうか。新しい形の協調性、人間の新しい知恵、“どうしようもなく寛容”な精神を培っていくのではないかと思っています。
(ネットワークにより)国境を越えて、すべての言葉が翻訳可能な時代になっていき、今現在はユニバーサルなマナーや様式を学びつつあるという意識が芽生えつつある状況なのだと思います。
みんながレオナルド・ダ・ヴィンチになれる……“ルネッサンス・マン”になれる時代が到来しつつあるのではないでしょうか。僕個人としてはデジタル・テクノロジーが人間をヒール(癒す)できるかどうかを見つめていきたいと思っていますが。
【*1】
『ELECTRIC GARDEN』
1985年にカセットブックとして小学館より発売された。楽曲をバックにポエトリーを読み上げている作品を収録したカセットにニューヨークのアーティスト、マーク・コスタビのイラスト付きのテキスト・ブックがカップリングされている。
▲ 本文へ戻る
【*2】
「THIS」
1983年に佐野元春のプライベート・マガジンとして発行され、1994年の秋にリニューアルを遂げて復刊した。現在は季刊。
▲ 本文へ戻る
【*3】
ジャック・ケルアック
アレン・ギンズバーグに並ぶビート派の代表的詩人、作家。代表作に「路上」(河出書房新社)、「ジャック・ケルアック詩集」(思潮社)など多数。
▲ 本文へ戻る
【*4】
『Pop Children with the New Machine』
1992年リリースされたアルバム『Sweet 16』に収録されている曲。「最新マシンを手にした陽気な子供たち」という邦題がつけられている。
▲ 本文へ戻る
![]()