
|
|
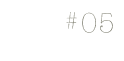 |
|
 |
 |
::: まず最初に、初めて『Visitors』を聴いたときの経緯を教えてください。
近田 当時、なにかの雑誌で新譜のコメントを書く仕事をしていて、たまたま「コンプリケイション・シェイクダウン」を聴いたんですよ。最初は……すごく新しいことに挑戦してるなって気がしましたね。だからアルバムとしてよりも、僕はあの曲がきわめて記憶に強く残っています。
::: ヒップホップ的なアプローチとしての興味ですか?
近田 ええ。ヒップホップがロックに変わる表現になると気づく前、そもそもシュガーヒルとかのパーティ・ラップは好きで聴いてたんですよ。自分で日本語で詞を書く場合、英語に比べて同じ時間の中に詰められる情報量が少ないから、ラップで日本語をリズムに刻み込んでいくやり方は何かあるんじゃないかって、ずっと考えていて。だからヒップホップというカルチャーにノックアウトされる前に、まずラップという手法に興味があったんです。それで「コンプリケイション・シェイクダウン」を聴いたときに、そういうエッセンスをヒントに得ているなという思いを強く感じて。
::: 佐野元春については、その前後、どういう認識を持ってましたか?
近田 たぶん、どんなアーティストも、本質は自分を変えたいと思っても、ずっと変わらないと思うんです。ただ、何かを経験することによって、自分の中でそれまで禁じ手だったものを解除するとか、そういうことで表現の幅が広がるときがある。彼にとって、あの時代の経験は、そういう意味で表現の柔軟性につながったと思う。
::: 日本のポップ・ミュージックの変遷の中で、この作品を定義するならば、どういう位置づけになると思いますか?
近田 やっぱり、洋楽を聴いてきた人が日本語の音楽をやるという不便さを、それぞれがそれぞれの方法で解放しようと努力してきて、そういう中のひとつのヒントとして、その後の人たちに与えた影響はあると思います。日本語で表現するポップ・ミュージックの可能性を、ひとつの選択肢として示唆したという点において。
::: 当時の日本のヒップホップとは、言葉がサウンドとともに一体化する過程……よりも以前の試みだったような気がします。
近田 うん、以前ですよね。みんな、とにかくもっと日本語でスピーディに表現できないかって考えていたと思う。だけど、なかなかそれはうまくいかなくて。ただ、結果的にいまの日本でヒップホップみたいな音楽がちゃんとビジネスになって、しかもサウンド的にすごい連中がこんなに出てくるとは想像してなかった。だから、あの時代のものと現在の間には、実はそんなにつながりがないんだって気がする。
::: では、そこに何があったと?
近田 最初にヒップホップに興味もって日本でやろうと思ってた人たちより、そのあと主流になっている人たちは、もっと肉体的ですよね。僕らの頃は、もっと頭で考えていたというのかな。そういうところから入ってきたんだけど、いまはそれよりも……あんまり考えないで作ってるんじゃないの? そういうものが主流になってる。なんとなくカッコよければいいって。それはそれでいいと思うんだけど、僕なんかはヒップホップらしさよりもそれが意味するものが何なのか、そして、それを日本の文化の中で不自然ではない形にすることはどういうことなのか、一種翻訳的な気持ちがあったんだけど。
::: むしろ、いまは形から入っている、と。
近田 ええ、やっぱりBボーイ・ファッションとか、そこから入ってきてる人の方が多いでしょ? 僕なんかから見てみると、それってゴッコみたいに見えちゃって、ヒップホップ本来のこだわり……リアルとかメッセージ性がどこかですり替えられているような気になっている。昔の僕の想像では、ヒップホップが日本に根付くとしたらアメリカのスタイルとは別の何か……日本語に対してオリエンテッドなビートがのるのかなって思ってたんだけど、実はそうではなくて、アメリカで作られているトラックみたいなものにどうやって日本語のツジツマを合わせるかという作り方になっちゃった。それは僕とはまったく考えが違ってる。そういう意味で、最初の頃は洋物と違うものを作ろうという気持ちが強かったのが、いまはヒップホップらしさみたいなものが主流になって。その間にはつながらないものがあるような気がする。
::: ビブラのライムとリップ・スライムのライムは別のものですよね。
近田 まったく別なものです。――耳障りにならない言葉で、単語で割っていく。近田 そこがね、それこそ佐野君が最初こういうことに挑んだときと違う。自分の考えを日本語で伝えるための手立てとしてラップというフォーマットがあったとして、本来は喋ることの延長線上にあるはずの音楽が、まったく関係ない音楽になっちゃってる部分はあると思う。だから最近、逆に面白いと思うのは、ヒップホップ的なライミングに似た喋り方をする若者がいますよね。
::: 普段の日常会話で。
近田 うん。短い単語単語で、体現止めみたいに。言い回しもヒップホップ的 で「なんだか今日は余裕で寒いぜ」とか(笑)。たぶん、いまのヒップホップが生まれた後で、そこから出てきた喋り方だと思うけれど……でも、そういう発展もあるのかなって、それはそれで逆に面白いなって。
::: 佐野自身、当時のニューヨークで、ラップはユニバーサルなストリートの遊びだったと述べてますが、そう考えると初期の“実験”だったのかもしれません。
近田 それは僕もすごくそう思います。あの時代はみんな、とにかく実験してみたくなる物事が多かった。機材的にもそうですよね。いま日本にいれば何でも手に入るし、それ以上にソフト化されているから、ノートブックが一台あれば誰でもそこそこなものが作れる環境にある。昔みたいにサンプリング・マシンが100万円以上の時代じゃないから、やろうと思えば何でもできる。でも、当時は機材ひとつ手に入ると、何か新しいことができるんじゃないかっていう実験心が今とは比べ物にならないくらいわき上がっていた頃で。みんな、そうだったと思いますよ。
::: ちなみに86年、近田さんは“プレジデントBPM”では「マスコミュニケーション・ブレイクダウン」という曲を発表してますが、ひょっとしてこのタイトルは……。
近田 そうそう(笑)あとで考えたんだけど、佐野君の曲からすごくヒントを得ていると思う。出した時は忘れてたんだけど、しばらくしたらそうかもしれないって気がしてたんですよ。でも、意識してつけたわけじゃなくて……レッド・ツェッペリンに「コミュニケーション・ブレイクダウン」って曲があるじゃん。で、その頃、ヒップホップに結構ハードロックっぽい音を入れるのがあったから、そういうこともあって。あと、ヒップホップだから、なんかメッセージが入ってないとマズいかなって……僕、ほんとはまったくメッセージがない人間なんですけど。
::: でも、すごく説得力ありましたよ。
近田 それを技術で補いたいって気持ちがあったんでしょうね。それでもっともらしいタイトルを考えたんだけど、あとから考えたらコレは、おそらく佐野君の曲の響きが元になってるなって思いました。――もしかしたら……と思ってたんです。近田 だから、それだけあの曲は強かったんだろうね。最初に聴いてから1〜2年たってるけれど、自分の中できっと根の部分に残ってたんでしょう。
::: では最後に、佐野へのメッセージを。
近田 2年前の大晦日、年越しそばを食べようと思って蕎麦屋さんに行ったら、偶然に会ったんですよ。以来、会ってないですけれど、また偶然に年越しそばでも食べられたらいいなと(笑)いつまでも好奇心を感じられる音楽を作り続けてほしいなと思います。
聞き手: 増渕俊之 |
|
 |
|
Contact Us | Copyright 2003 M's Factory Music Publishers, Inc. All rights reserved.
|
|
 |

